【ストアカ オンライン講座】
「音による風景画」 表題音楽の世界
2022年2月13日(日)
zoomによるオンライン授業
講師:中川つよし(和光大学非常勤講師)
音楽に込められた「視覚的な美」を探求します。

参加費
【ストアカ オンライン講座】

【ストアカ オンライン講座】
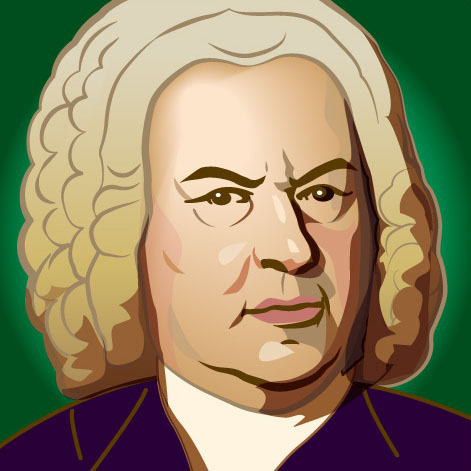
【ストアカ オンライン講座】

【ストアカ オンライン講座】

【ストアカ オンライン講座】

【ストアカ オンライン講座】

 ボワモルティエの4声のソナタを演奏中 |
 客席を望む。 |
 大合奏。 |
 ゲストによるヴィオラ・ダ・ガンバ演奏。 |
 合奏を指揮する中川講師。 |
2018年3月3日(土)
北とぴあ
2016年3月21日(月・祝)
北とぴあ
後援:和光大学
2014年3月23日(日) 北とぴあ
2012年2月5日(日) 北とぴあ
2011年11月11日(金) 殿上湯
2010年10月8日(金) 殿上湯
2009年1月20日(火)
さいたま新都心:NHK文化センターさいたまアリーナ教室